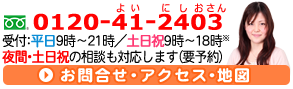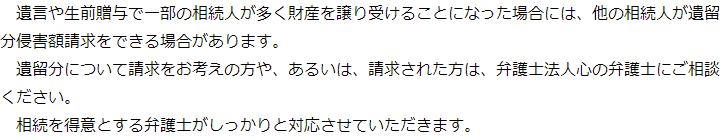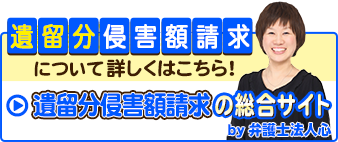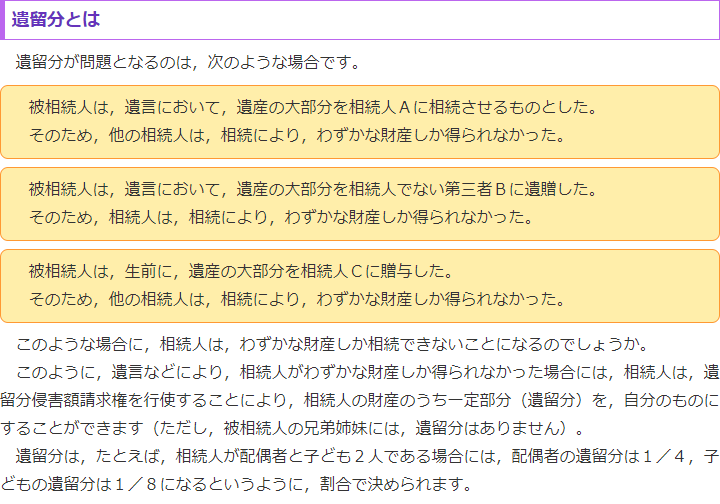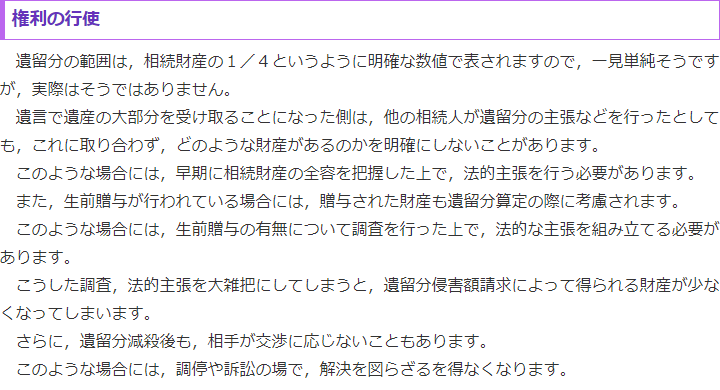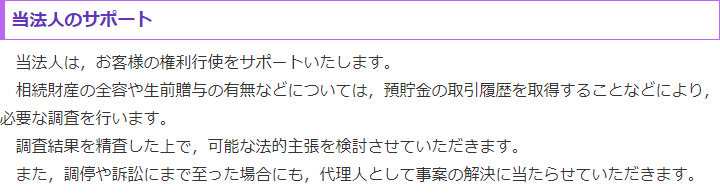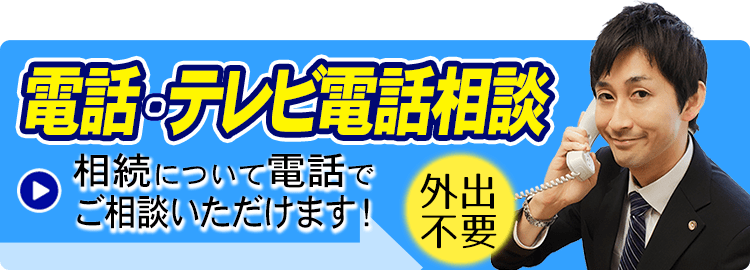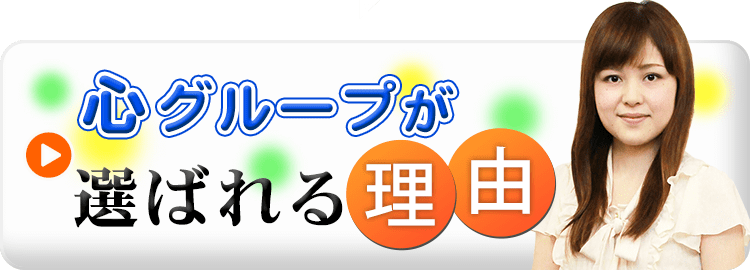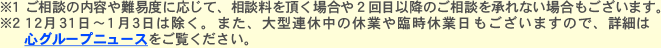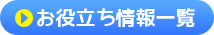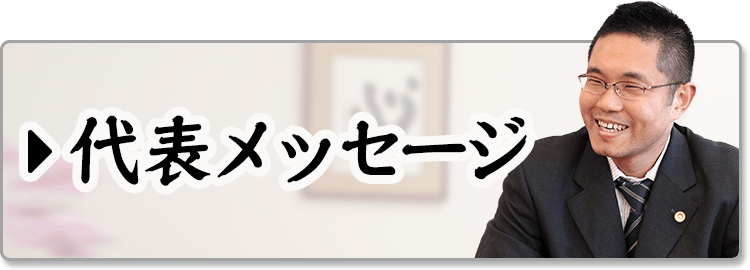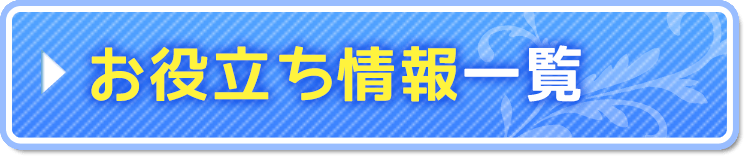遺留分侵害額請求
アクセスを大事にしています
アクセスが良くないと、来所していただく度にお客様の負担となってしまいます。当事務所は岐阜駅の近くにありますので、お気軽にご利用いただけるかと思います。
遺留分を請求する際の注意点
1 遺留分を請求する期限

一部の相続人には遺留分が認められており、遺言書による遺贈や生前の贈与等で遺留分が侵害される場合には、遺留分を侵害された相続人は、侵害された部分を取り戻すための請求をすることができます。
ただし、この遺留分の請求には期限があるため注意が必要です。
まず、自らの遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求をする必要があります。
この「自らの遺留分が侵害されていることを知ったとき」には、具体的な金額までを認識している必要はありませんので、例えば、遺産の大部分を他の者が相続することになっている遺言書の内容を認識していれば、「自らの遺留分が侵害されていることを知ったとき」にあたるといえるでしょう。
また、相続が開始してから10年以内に請求をする必要もあります。
相続を開始したときとは、基本的に、被相続人が亡くなったとされる日を指します。
2 遺留分を請求する際のポイント
このように遺留分を請求するには期限がありますから、遺留分の請求をするにあたっては、期限内に請求をしたという証拠を残しておく必要があります。
すなわち、遺留分の請求を受けた者が、訴訟で「期限までに遺留分の請求を受けていなかった」と主張してくる可能性があることから、遺留分を請求する側は、期限内に請求をしたという証拠を残しておく必要があるのです。
実務上は、配達証明を付けた内容証明郵便で、遺留分を請求する旨の通知書を送るということが行われています。
この通知書の中には、少なくとも、誰から誰への請求であるのか、どのような内容の行為によって遺留分を侵害されたのか、遺留分の請求としてどのような内容の請求をするのかといった事項を記載するようにしてください。
内容証明郵便の作成方法にはルールが決まっていますし、書類を作成して郵便局に持ち込む方法や、インターネットで作成して送付する方法等、様々な方法があります。
内容証明郵便の送付方法が分からない場合には、しっかりと調べた上で送付するようにするとよいかと思います。
遺留分権利者の範囲
1 すべての相続人が遺留分権利者にならないことに注意

相続において、相続人に認められた最低限の保障分を遺留分といいますが、この遺留分はすべての相続人に認められていないことに注意しましょう。
具体的には、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。
法律上の根拠は、民法第1042条です。
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)額を受ける」と規定されており、兄弟姉妹が相続人である場合を遺留分が認められるケースから明確に排除しています。
兄弟姉妹の代襲相続人(被相続人の甥姪など)についても、その者らに兄弟姉妹に認められていない遺留分を認める理由はありませんから、同様に、遺留分は認められないことになります。
このように、すべての相続人が遺留分権利者にならないことに注意しましょう。
2 遺留分権利者となる相続人の具体的な範囲
反対に、兄弟姉妹(およびその代襲相続人)以外の相続人は、遺留分権利者になります。
具体的には、被相続人の配偶者、子どもは遺留分権利者となります。
子どもについて代襲相続が発生していた場合には、その代襲相続人(孫やひ孫)に遺留分を認めない理由もありませんから、その者も遺留分権利者になります。
尊属(両親や祖父母)が相続人である場合には、尊属も遺留分権利者となります。
3 遺言書を作成する場合には、遺留分の範囲に注意
遺留分が問題になる主なケースは、亡くなった方の遺言書の内容が、相続人の遺留分を侵害しているようなケースです。
遺留分を侵害するような内容の遺言書である場合には、相続で争いになる可能性がありますので、これについての検討や工夫をしておく必要があります。
その検討のために、遺言書を作成する際には、誰が遺留分権利者となるのかを確実に把握しておくことは基本的な事項といえるでしょう。
仮に、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけだとしたら、上述のとおり、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺留分のことを考慮することなく、自由に遺言書の内容を決めて差し支えないといえます。
「配偶者に、すべての財産を相続させる」という遺言書であったとしても、遺留分についての問題は生じないでしょう。