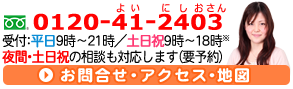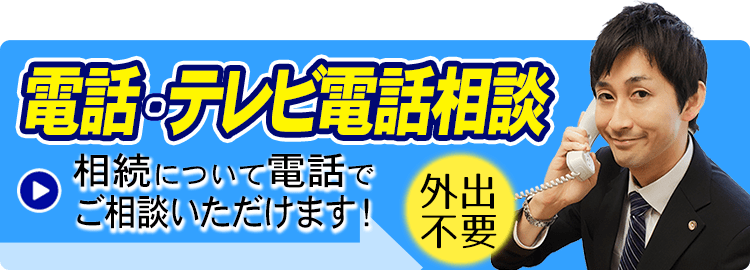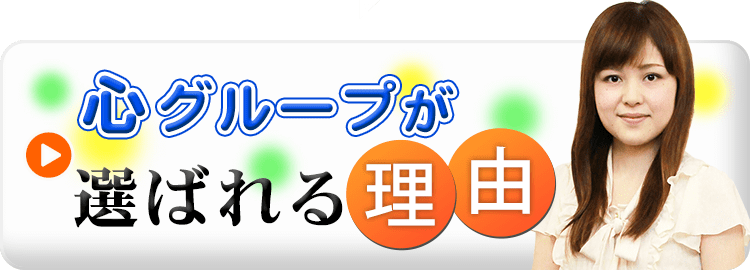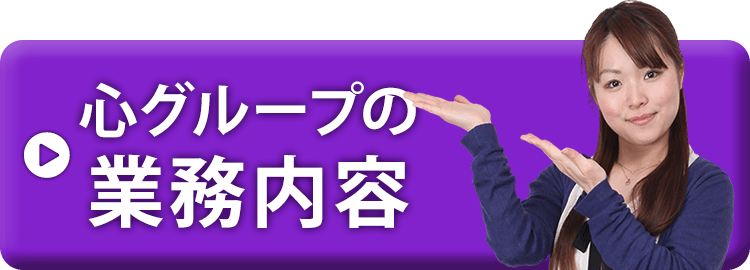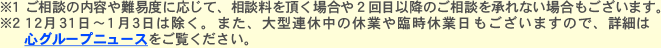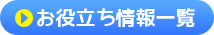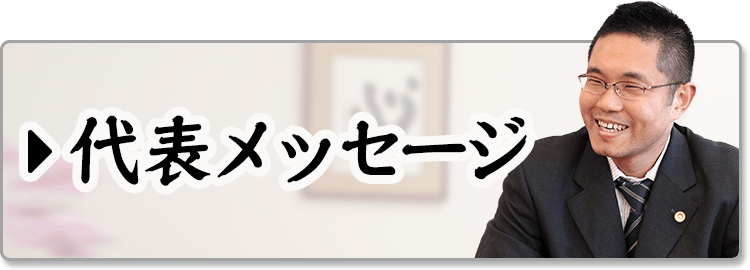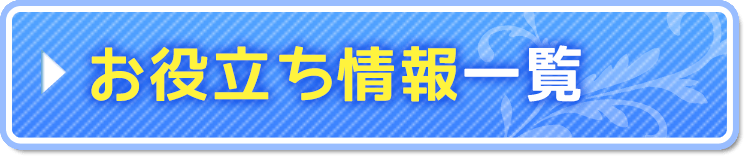相続の費用
1 相続手続きにかかる費用

相続手続きにかかる費用としては、手続きに際して必ず必要となる費用、手続きを専門家に依頼した場合に必要となる費用に大きく分けられます。
手続きに際して必ず必要になる費用は、手続きを行う財産によって異なります。
また、手続きを専門家に依頼した場合に必要となる費用については、どの専門家に依頼するかによって異なります。
かつては、弁護士、司法書士、行政書士等、専門家の種類によって、費用の決め方が異なることもありましたが、近年では、専門家個人ごとに、それぞれ独自の基準で費用を決めるようになってきています。
2 手続きに際して必ず必要となる費用
- ⑴ 不動産
-
不動産については、法務局において登記の手続きを行う必要があります。
登記に際しては、登録免許税が課税されます。
相続登記の場合は、不動産の最新年度の固定資産評価額の0.4%、遺贈の登記の場合は、相続人が取得するときは不動産の最新年度の固定資産評価額の0.4%、相続人以外が取得するときは不動産の最新年度の固定資産評価額の2%を基準に課税されることになります。
なお、税制改正により、一定の相続登記または遺贈の登記については、2025年3月31日まで登録免許税の免税措置がとられています。
また、登記に際しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍等、相続関係を明らかにする戸籍を提出する必要があります。
これらの戸籍を取得するに当たって、1通当たり450円から750円の費用を支払う必要があります。
- ⑵ 預貯金
-
預貯金の払戻しについては、基本的には、多額の費用負担が生じることはありません。
払戻しに際し、解約手数料等が発生することが多いですが、1件あたり何百円かの費用負担に過ぎないことが多いです。
預貯金の払戻しに際しても、戸籍を提出する必要がありますので、新たに戸籍を取得する場合には、1通当たり450円から750円の費用を支払う必要があります。
- ⑶ 有価証券
-
被相続人名義の有価証券については、相続人の誰かに名義変更する手続きをとるか、売却し、売却代金を払い戻す手続きをとることとなります。
売却にあたっては、証券会社に対して手数料を支払う必要があります。
また、売却の対象となる株式が、単元株が定められた株式であり、単元未満の株式数で売却する必要がある場合には、売却時の手数料が加算されることとなります。
有価証券の手続きについても、戸籍を提出する必要がありますので、新たに戸籍を取得する場合には、戸籍を取得するための費用が必要になります。
3 手続きを専門家に依頼した場合に必要となる費用
相続の手続きを専門家に依頼した場合には、専門家に対して費用を支払う必要があります。
かつては、おおむね、司法書士や行政書士については、作成した書類の分量等により手数料を負担することとなり、弁護士については、取得する遺産の評価額等に基づき、着手金、報酬金を負担することとなる傾向がありました。
しかし、近年では、案件次第で、司法書士や行政書士であっても、遺産総額の何%という形で費用を定めたり、弁護士であっても、作成した書類の分量等により手数料の負担としたりする例も増えてきています。
こうした費用の基準は、専門家個人で異なりますので、依頼する前に、費用の算定方法等を確認するのが望ましいでしょう。
4 相続手続きについてのご相談
私たちは、岐阜の相続手続きの案件を広く取り扱っています。
当事務所は、岐阜駅北口から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分のところに事務所を設けておりますので、相続手続きの件でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。