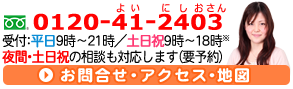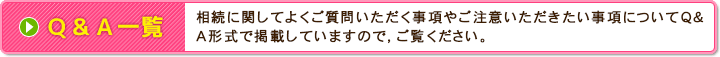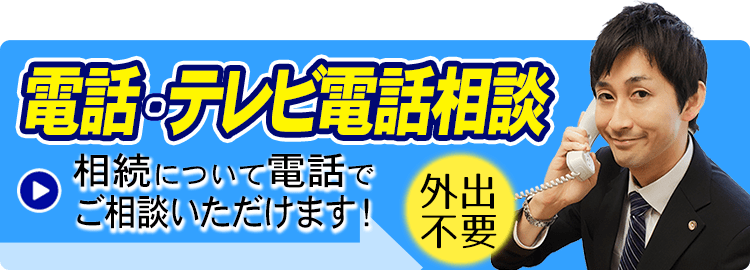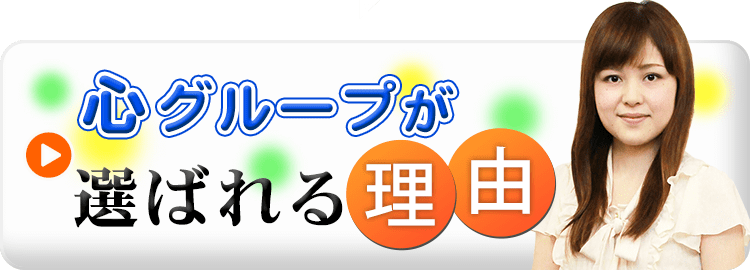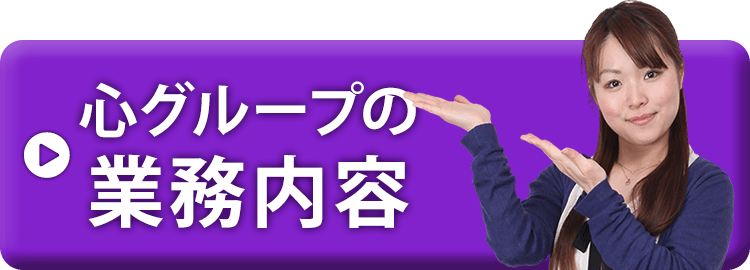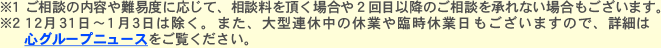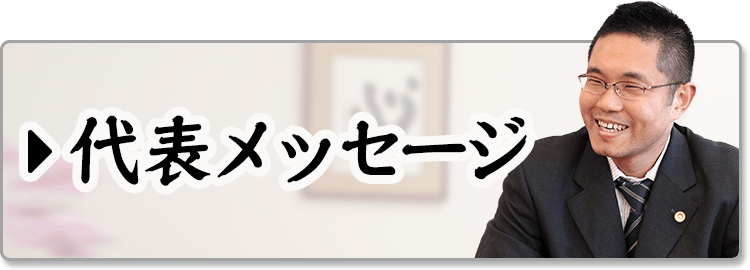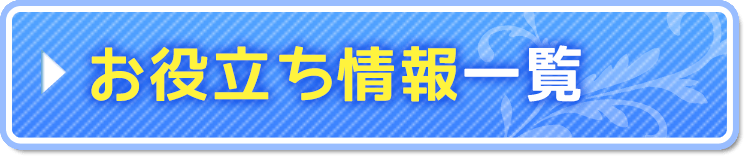相続した不動産を共有名義にする場合のデメリット
1 使用の制限などのデメリット
複数の相続人が同じ不動産を相続する場合、複数の相続人でその不動産を共有することになります。
共有の状態というのは、たとえば、「不動産のここから、ここまではどの共有者のもの」というのではなく、共有者それぞれがその持分に応じて全体を所有することになるため、共有者が単独で使用する方法を決めるということができない場合があります。
自分の持分を超えて使用したい場合、他の共有者に対して、その使用に見合った対価を支払わないといけない場合もあります。
このように、共有状態だと、単独の所有者であれば自由に決められる不動産の使用方法を制限されたり、払う必要のない費用を負担しなければならなかったりするおそれがあります。
さらに、不動産を売却するなどの処分をしようとすると、共有者全員の同意が必要になりますが、他の共有者が、売却自体や、その売却金額による売却に応じてくれるかどうかは分かりません。
たしかに、共有の状態でも自分の持分のみを売却することはできますが、この場合には、他の共有者からの同意は必要ないものの、そのような不動産を買い取る者は限られますし、不動産全体を売却するよりも割安でしか売却できないでしょう。
他方、このように持分のみを譲渡することができるということは、他の共有者からみると、自らが知らないうちに、共有する相手が変わっている可能性もあるということになります。
そのため、当初は、相続人間の見知った相手との共有であったとしても、持分が譲渡されたことにより、知らない相手との間での共有になってしまうおそれがあるということです。
そのような場合には、上記のような、使用についての協議や、売却などの処分についての協議が円滑に進められなくなるおそれがあります。
相続で不動産を共有とすることには、このようなデメリットがあるといえます。
2 共有者が増えるおそれ
不動産を共有している相続人が亡くなった場合、その持分が相続の対象になるため、その被相続人に複数の相続人がおり、そこでも不動産を共有とした場合、さらに共有者が増えることになります。
共有者が増えることで考えられるデメリットは、上記のようなものが考えられますが、共有者が増えれば増えるほど、そのデメリットが顕在化するおそれが高くなりますし、同意を得るためのコストも高くなってしまいます。
このほうに、当初の相続人間では、たとえば兄弟姉妹などで意思疎通が容易にできる関係であったとしても、それらの者に相続が発生することで、共有者間の関係が疎遠であったり、仲が悪かったりという状況が生じてしまうかもしれませんので、注意しなければなりません。
3 不動産は単独所有が無難
このような問題を生じさせないためにも、不動産の共有はできるだけ避けた方がよいと思います。
もちろん、相続人間で不動産を売却することが合意できており、一時的に共有とすることは問題ないと思います。
ですが、不動産を長期にわたって共有とすることは、上記のような問題が生じるため、避けるべきでしょう。
相続不動産を共有名義にしないためには、たとえば、遺産分割で相続人1人が取得することにして、他の相続人には、本来取得するはずであった分の支払いをするという方法があります。
不動産を取得したいと思っていても、このような代償金を支払うことができない場合には、共有とするのではなく、不動産を売却して得た金額を分けるなども検討しなければなりません。
ここで問題になるのは、遺産分割が審判手続きでされることになった場合には、不動産を共有で取得することになる可能性があるという点です。
すなわち、不動産を取得して代償金を支払いたいという複数の相続人が競合したときや、だれも不動産を取得したいとの希望を出さなかったときなどは、裁判所は、当事者間の平等のために、不動産を共有で取得するように決める可能性があります。
そうすると、なるべく避けるべきである不動産の共有という状態が生じることになってしまいます。
このような事態になってしまうことを避けるためにも、相続人間ではしっかりと話し合って、それぞれになるべくリスクが生じないような分割方法を話し合っていく必要があります。
相続で必要となる実印について 印鑑登録ができない場合の相続手続きの進め方