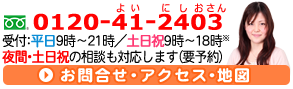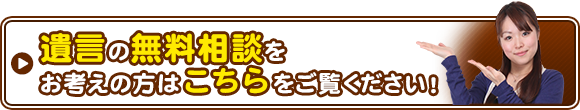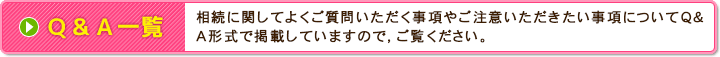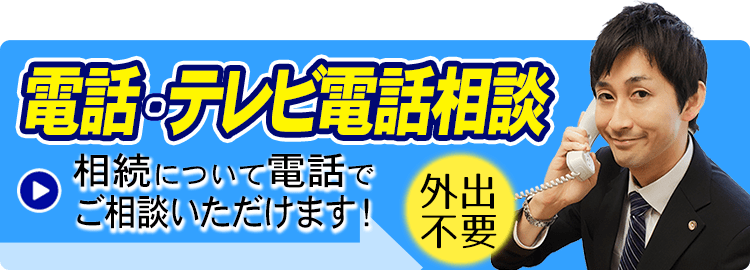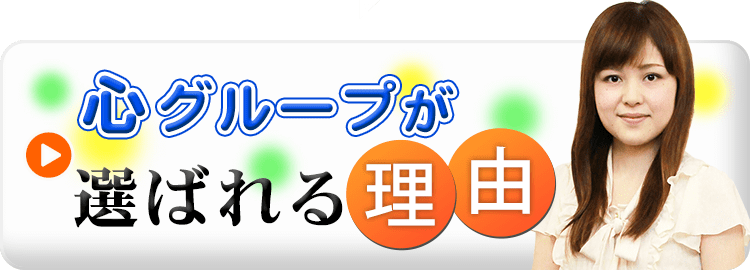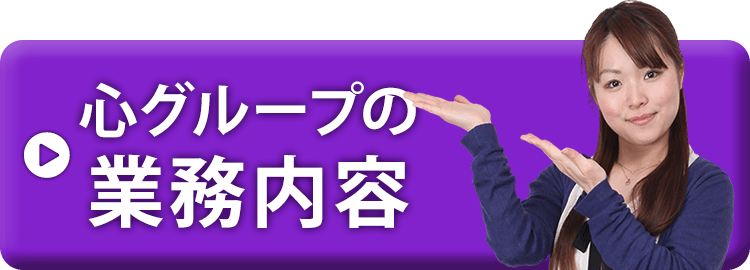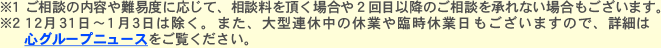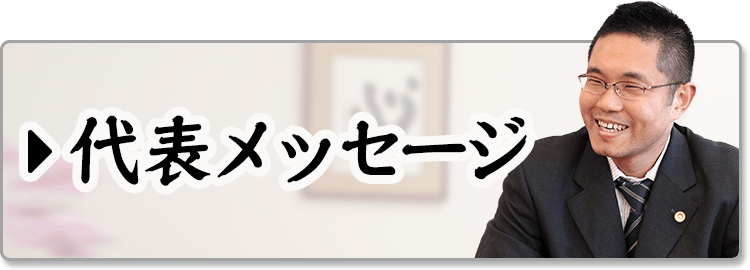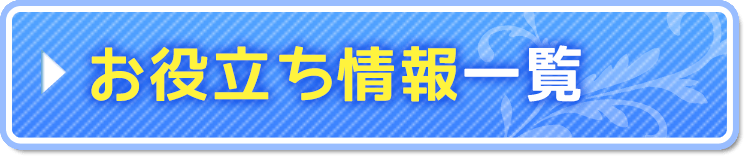遺言書を作成する際の注意点
1 遺言書を作成する際に注意すべきことは非常に多い
ご自身の相続対策のために、遺言書を作成しておきたいと思われる方は多くいらっしゃるかと思います。
ただ、弁護士としてお客様からのご相談に応じている経験からすると、相談前にご自身で遺言書を作成されている場合に、遺言書が適切に作成されていたというケースは稀だと感じています。
相続というのは、人生で何度も経験することでもないですが、他方で、周囲から相続に関する話自体はよく聞くものでもありますので、専門家に相談をせずに自分で手続きを進めても大丈夫だろうと考えてしまいがちです。
しかし、相続を経験したことがあるという人からの話を聞いたといっても、相続に関する状況は千差万別ですので、その方の相続では適切だった対応方法が、他の相続において適切であるとは限りません。
そのため、遺言書を作成すること自体は、相続において非常に効果の高いことではあるのですが、相続対策のために遺言書を作成するという場合は、細心の注意を払って、遺言書を作成する必要があります。
以下では、遺言書を作成する際の注意点について、いくつか紹介します。
2 どの方式で作成するのか
遺言書には、作成する方式がいくつかあります。
主なものは、自筆で作成する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言というものがあります。
どちらがよいのかというのは、それぞれの方のケースによります。
自筆証書遺言は、一部を除き、遺言書を原則自分で記載する必要がありますので、高齢の方で字を大量に書くのが難しいという方にとっては作成が容易ではない場合があります。
また、専門家へ依頼をせずに自筆証書遺言を作成する場合には、法律上の要件を満たしているかどうかや、亡くなった後の相続手続きが円滑に進められる内容になっているかどうかなど、内容面での不備があるおそれがあります。
他方で、自筆証書遺言は、紙と筆記用具さえあれば作成をすることができますし、作成のための費用もほとんどかかりませんので、遺言書の内容を見直すことが予定されていたり、まずは手軽に作成してみたいと考えたりされている方にとっては望ましい方式だといえます。
ただし、自筆証書遺言は、保管している過程で火災や地震などによって焼失・紛失してしまったり、家族にその存在が知られていなかったりするリスクがあり得ます。
つまり、せっかく作成してもその役割を果たせないまま、相続人全員で遺産の分け方について協議する手間が生じてしまうこととなります。
このリスクに対しては、専門家に作成を依頼する場合には、専門家によっては事務所の金庫で保管をしてもらうことができる場合がありますし、法務局での保管制度を利用して、遺言書の内容を保管しておいてもらうことで、ある程度対処することが可能になっています。
参考リンク:法務省・自筆証書遺言書保管制度
他方で、公正証書遺言で作成する場合においては、公証人という法律のプロに作ってもらえるので、法律上の要件を欠く遺言書を作成してしまうというリスクを避けることはできます。
遺言書の文案は公証人が作ってくれますから、遺言者は遺言の内容を伝えるだけでいいですし、作成の際には、署名と実印での押印をすればよいので、自筆の場合に比べてご自身の負担は少ないといえます。
遺言書の保管に関しても、作成した遺言書の原本は公証役場の金庫で保管してもらえますし、作成した際に通常渡される正本と謄本については、紛失してしまっても、後日、請求すれば再度作成してもらうことができます。
しかし、公正証書で遺言を作成する場合には、内容に応じて、遺言者や相続人の戸籍や、不動産などの財産に関する資料などを準備する必要があるため多くの手間がかかる面もありますし、作成するためにはある程度の費用もかかります。
それに、基本的には、公証人は、遺言者にとって望ましい遺言の内容がどのようなものなのかということについてのアドバイスはしてくれません。
このような点についてアドバイスを受けたいと思うのであれば、弁護士や税理士などの他の専門家に相談をする必要があります。
なお、公正証書の作成は基本的に公証役場で行うものですが、遺言者が寝たきりの状態などで外出できない場合には、作成費用は高くなってしまいますが、公証人に自宅や施設まで出張してもらうことが可能です。
3 遺留分についてどのように配慮するのか
相続人の一部には、遺留分という権利が認められています。
遺留分というのは、遺言書の内容が平等ではなく、被相続人からの他の相続人へ多額の生前の贈与などがあった場合に、最低限の財産を取得することを認められる権利であり、遺言者であっても遺留分についての権利を奪うことはできません。
そのため、相続において、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、相続人同士でトラブルとなるリスクがあります。
そこで、遺言書を作成する際には、遺産全体や相続人の関係を確認し、遺留分を侵害する内容となっていないかをチェックする必要があります。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言書を書いてはいけないというわけではありませんし、このような内容の遺言書であっても、法的には有効です。
場合によっては、どうしても財産を渡したくないという相続人もいるかと思います。
そのような場合には、遺言書を作成する時点で、残された相続人がなるべくトラブルに巻き込まれないように、あるいはトラブルに巻き込まれたとしても、なるべく被害を負わないようにする工夫が必要です。